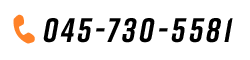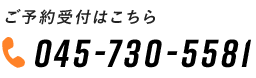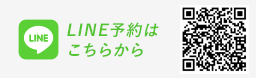顎関節症が姿勢に影響される理由
まず、顎関節(がくかんせつ)は耳のすぐ前にあり、口を開けたり閉じたりする際に使われる関節です。日常の姿勢が悪いと、この関節に負担がかかりやすくなり、痛みや不快感(顎関節症)が生じる原因となります。
顎関節症になりやすい姿勢
•頭が前に出る「頭部前方位姿勢」は、スマホやPCを長時間見る際に多い姿勢です。この姿勢では首の筋肉が緊張し、顎にも負担がかかりやすくなります。
•猫背になると、首や肩、顎周りの筋肉が緊張し、顎の開閉に影響が出ることがあります。
顎関節症かなと思った時のセルフケア
1. 顎のリラックスを心がける
無意識のうちに食いしばりや歯ぎしりをしていることが顎関節症を悪化させる原因となります。普段から顎の力を抜き、筋肉の緊張を和らげる意識を持つことが重要です。
•普段から歯を軽く閉じる:上下の歯を軽く合わせて、力を入れずに顎を閉じる状態を保つようにしましょう。「上下の歯が触れないように」意識するのも効果的です。
•ストレス対策:食いしばりや歯ぎしりはストレスと関係が深いため、リラックスする時間を設けたり、深呼吸をするなどしてストレスを軽減しましょう。
2. 顎周りの筋肉をほぐすセルフマッサージ
顎周りの筋肉、特に咬筋や側頭筋が緊張していると、顎関節に負担がかかりやすくなります。セルフマッサージで筋肉の緊張を和らげましょう。
•咬筋のマッサージ:頬骨の下にある咬筋(奥歯をかみしめたときに動く筋肉)を指で優しく押しながら、円を描くようにマッサージします。
•側頭筋のマッサージ:こめかみ部分にある側頭筋も、指の腹で優しくほぐします。こめかみから頭頂部に向けて円を描くようにマッサージすると、リラックス効果が得られます。
3. 顎関節のストレッチ
顎関節周りの筋肉や関節の柔軟性を保つために、ストレッチも効果的です。
•顎の前後運動:下顎を前に軽く突き出し、次に元の位置に戻す動作を繰り返します。無理に動かさず、軽く伸ばすイメージで行いましょう。
•顎の横方向ストレッチ:下顎を左右に動かして、顎周りの筋肉をほぐします。ゆっくりと行い、どちらかに強く引っ張らないよう注意してください。
•口を開け閉めする運動:「イー」と「アー」の形で口を大きく開けたり、軽く閉じたりすることで、口周りの筋肉をバランスよく使うことができます。
4. 姿勢の改善
顎関節症は、日常の姿勢にも大きく影響されます。首や肩、背中の筋肉のバランスを整え、良い姿勢を保つことが予防につながります。
•首・肩のストレッチ:首の筋肉が緊張していると顎関節に負担がかかりやすくなります。首をゆっくりと回したり、肩甲骨を引き寄せるストレッチを行いましょう。
•猫背やスマホ姿勢に注意:前かがみや首を前に突き出す姿勢は、顎関節に大きな負荷をかけます。デスクワークやスマホを使うときは、肩を引き、頭が肩の真上にくるような姿勢を意識し、デバイスの高さを調節しましょう。目線の高さに調節するだけで顎関節にかかる負担を軽減します。
5. 咀嚼の習慣を見直す
咀嚼の方法や食事の取り方も、顎関節に影響を与える要因です。以下のポイントを意識することで、顎関節の負担を軽減できます。
•左右均等に噛む:片側だけで噛むと、筋肉のバランスが崩れて顎関節症状が悪化しやすくなります。左右均等に噛むように心がけましょう。
•硬いものや粘り気のあるものを控える:硬い食品や粘り気のある食べ物は、顎に強い力がかかり、顎関節に負担をかけやすくなります。柔らかいものを中心に食べることが、顎の負担を減らすために効果的です。
6. 食いしばりや歯ぎしりの対策
無意識のうちに食いしばりや歯ぎしりをしている場合、夜間用のマウスピースを使用するなどの対策も効果的です。
•マウスピースの使用:歯科で作成してもらえる夜間用のマウスピースは、食いしばりや歯ぎしりから顎を保護する役割を果たします。
•日中も顎のリラックスを意識:特に集中しているときに食いしばりが生じやすいです。自分が力んでいないか意識するようにしましょう。
まとめ
顎関節症を防ぐためのセルフケアは、日常生活での小さな習慣や姿勢を意識することから始められます。筋肉の緊張をほぐし、姿勢を整え、顎への負担を軽減することが重要です。症状が改善されない場合や痛みが強い場合は、無理せず専門家に相談することをおすすめします。