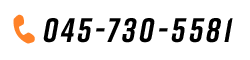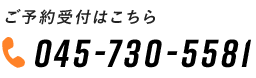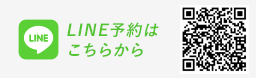登山初心者の方にとって、 「高山病」 は意外と知られていないリスクのひとつ。
標高が高くなると酸素が薄くなり、身体が適応できずにさまざまな不調が現れます。
「せっかく登ったのに、頭が痛くて楽しめなかった…」 なんてことにならないために、
今回は 高山病の症状と予防・対策方法 を解説します!
1. 高山病とは?原因と発症しやすい標高
高山病(急性高山病:AMS)は、 標高2,500m以上の高地で発症しやすい 体調不良のことです。
▶ 高山病が起こる原因
✔ 気圧の低下 → 体内の酸素が不足
✔ 体が酸素不足に適応できず、自律神経が乱れる
✔ 脳や肺の血管が膨張し、頭痛や息苦しさを引き起こす
⚠ 標高が高くなるほど酸素濃度は低下!
・標高3,000m:酸素濃度は地上の約70%
・標高4,000m:酸素濃度は地上の約60%
特に 標高が急激に上がると、体が順応できずに高山病になりやすい ため注意が必要です!
2. 高山病の主な症状(初期~重症)
高山病は 軽度の症状から始まり、悪化すると命に関わることも あります。
▶ 初期症状(軽度)
✅ 頭痛(ズキズキする痛み)
✅ 吐き気・食欲不振
✅ めまい・ふらつき
✅ 息切れ・動悸
✅ 手足のむくみ
☞ この段階で対策すれば、症状の悪化を防げます!
▶ 中等度の症状(注意が必要!)
✅ 強い頭痛(薬を飲んでも治らない)
✅ 嘔吐(食事や水分が取れない)
✅ 倦怠感・脱力感が強い
⚠ この状態になったら、すぐに高度を下げることが大切!
▶ 重症(危険!)
✅ 意識がもうろうとする
✅ 歩行困難・ふらつきがひどい
✅ 呼吸困難・チアノーゼ(唇や指が青紫色になる)
このレベルになると 高地脳浮腫(HACE)や高地肺水腫(HAPE) のリスクがあり、命に関わる可能性も。
すぐに標高を下げ、医療機関を受診する必要があります!
3. 高山病を防ぐための事前準備
高山病の 最大の予防策は「ゆっくり高度に慣れること」 です。
▶ ① 高度順応(アクライマタイゼーション)を意識する
✔ 1日に登る高度を500m以内に抑える
✔ 標高2,500mを超えたら1日1泊し、体を慣らす
✔ 登ったら少し下る「高度順応登山」を取り入れる
▶ ② 水分補給をこまめに!
高地では 体が脱水状態になりやすい ため、こまめに水を飲むことが大切。
✔ 1日3〜4Lを目安に摂取
✔ お茶やコーヒーは利尿作用があるため控えめに
▶ ③ 高カロリーな食事をとる
酸素が少ない高地では、体が多くのエネルギーを必要とします。
✔ 炭水化物(おにぎり・パン・パスタ)を意識的に摂る
✔ 脂っこい食べ物は消化に負担がかかるので控えめに
▶ ④ 深呼吸を意識する
✔ ゆっくりとした腹式呼吸で、酸素をしっかり取り込む
✔ 登山中は「息が上がらないペース」で歩く
▶ ⑤ 事前に「ダイアモックス(アセタゾラミド)」を服用
高山病予防のために、 「ダイアモックス」 という薬を事前に服用するのも有効です。
⚠ ただし、医師の処方が必要なので、登山前に相談しましょう!
4. 高山病になったら?対処法と応急処置
高山病の症状が出たら、 「無理せず、できるだけ早く対応する」 ことが大切!
✅ 登山を中止し、高度を下げる(300〜500m下るだけで改善することも)
✅ 深呼吸をして酸素をしっかり取り込む
✅ 酸素ボンベを使用する(登山用品店で購入可)
✅ 水分をしっかり摂る(脱水症状を防ぐ)
✅ 無理に食事をとらず、休息を優先する
⚠ 「少し休めば治るだろう」と放置すると悪化するので注意!
まとめ
高山病を防ぎ、安全に登山を楽しもう!
✅ 標高2,500m以上では高山病のリスクがある
✅ 初期症状(頭痛・吐き気・めまい)が出たら無理をしない
✅ 高度順応を意識し、こまめな水分補給をする
✅ 体調が悪化したらすぐに高度を下げる!
高山病は しっかり予防すれば防げる症状 です!
安全な登山のために、 事前の準備と対策 を忘れずに行いましょう!
もし 登山後に体調不良や違和感が続く場合 は、お気軽にご相談ください!
ひらの接骨院
232−0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町149−8
20時まで営業・駅から3分・駐車場完備・土日祝営業・緊急的な痛みなど即日対応
電話番号 045−730−5581