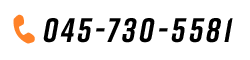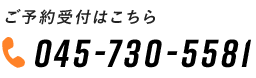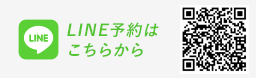当院では、2024年10月6日より巻き爪補正や爪切りのサービスを新たに開始いたしました。
矯正そのもので、爪の形をより正常へと近づけてあげることは除痛にもつながり、とても大切な施術の一つであること、また歳を重ねられ、足の指の爪が見えずに切れない方、または柔軟性を欠いて切りづらい方が非常に多いことが、30年の臨床の中でわかってきました。
ほぼ当院が採用する手法は、痛みのない施術ですので、巻き爪でお困りの方には是非とも体験いただきたいものではありますが、これだけで(矯正により)全てが解決できるような広告が多いこともあり、誤解のないよう掲載したいと思います。
実際、巻き爪矯正だけでは根本的な解決には至らないケースは多くあります。巻き爪によって指に痛みを感じている方にとって、矯正治療による改善は大いに期待できるものの、巻き爪を引き起こすさまざまな原因にアプローチしなければ、再発のリスクは高いままです。巻き爪が再び現れることを防ぎ、真の痛みの軽減を目指すためには、矯正だけで終わらせることなく、根本的な要因に対する理解と対策が求められます。
スマホ首の方が、スマホ利用時間を減らさなければ、首の治りが悪いように、巻き爪もその原因がいくつかあり根本的な部分を見直すことも必要なのです。
具体的には、巻き爪の原因には、日常の爪の切り方や履き物の選び方だけでなく、足指の硬さや体幹の筋力不足、骨盤の後傾といった全身的な要因が大きく影響している場合も多いのです。加えて、足指が十分に使えず、安定感が低下することでメカニカルフォース(力の伝達力)を十分に得られなくなることが、足指の負担を増やし、巻き爪の進行を助長する原因にもなっていると言われています。
患者さまがご自身の巻き爪の原因をしっかりと理解することが、改善への第一歩であり、再発防止のためにも重要なポイントです。巻き爪矯正だけではなく、全身のバランスや生活習慣に目を向け、一緒に改善策を見出していけることを願っております。
巻き爪(陥入爪)の原因はいくつかあり、日常生活の習慣や生まれ持った爪の形状が影響していることが多いです。以下の要因が考えられます。
-
爪の切り方
爪を深く切りすぎたり、端を丸く切ることで、爪が肉に食い込みやすくなり、巻きやすくなります。特に、足の爪は真っ直ぐに切ることが推奨されています。 -
靴のサイズと形状
サイズが小さく先端が狭い靴(特にハイヒールや先の細い靴)は、爪に圧力がかかり、巻き爪が発生しやすくなります。また、靴が大きすぎても、足が靴内で滑ることで爪が当たって変形の原因になります。 -
遺伝的要因や爪の形
爪が元々湾曲しやすい形状であったり、足の骨格の影響で爪に圧力がかかりやすい方は、巻き爪ができやすい傾向にあります。 -
足の動きと歩き方
歩行時の圧力が爪に不均等にかかることも原因の一つです。偏平足や外反母趾など、足の骨格や姿勢が影響しているケースも見られます。 -
乾燥と皮膚の状態
乾燥により爪が硬くなったり、柔軟性が失われたりすると、皮膚に食い込みやすくなり、巻き爪を引き起こすことがあります。 -
外的な衝撃
足の指をぶつけたりすることによって爪が変形し、巻き爪につながることもあります。 - 足の指の硬さ
足の指が硬くなると、体重や歩行時の圧力が均等に分散されにくくなり、その結果、爪への圧力が特定の部分に集中することがあります。これが爪の湾曲や変形を促し、巻き爪につながることがあります。足指を柔軟に保つためのストレッチやマッサージは、巻き爪の予防に役立ちます。
- 体幹の筋力不足
体幹の筋力が弱いと、姿勢が崩れやすくなり、歩行時の足の使い方やバランスが不安定になります。その結果、足先に過度な圧力がかかり、爪が変形しやすくなる可能性があります。体幹を強化することで、歩行時の全身のバランスが整い、巻き爪の予防にもつながります。 - 骨盤の後傾
骨盤が後傾すると、体全体の重心が後ろに偏りがちです。この姿勢では歩行時に足先への荷重が不自然にかかり、爪への圧力が強まることで巻き爪が進行することがあります。骨盤の適切なポジションを保つことが、巻き爪予防には重要です。
- 指を使えないことによるメカニカルフォースの不足
足指を十分に使えない場合、歩行や立位での安定性が低下し、自然な力の伝達(メカニカルフォース)が弱まります。この力の不足が原因で、爪への圧力が局所的にかかりやすくなり、巻き爪のリスクが高まります。足指の可動域や筋力を保つことは、足全体の安定性を向上させ、巻き爪の予防にもつながります。