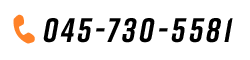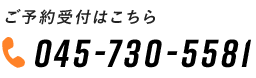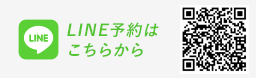“週替わりの身体”と向き合うプロの戦略
インターナルモデルと自己調整力
「その週に入って、毎回自分がしたいスイングが変わったりする」
AIG全英女子オープンに出場されていた西郷真央プロが、井上莉花プロのYouTubeチャンネル《Stance tv》の中で語ったこの一言は、ゴルフにおける“スイング”という言葉の捉え方を、根底から揺さぶるものだった。
彼女は、2025年のシェブロン選手権で日本人として初の優勝を飾ったメジャーチャンピオン。
その頂点に立つ選手が、“スイングは固定された形ではなく、変化するもの”と捉えている。
私はその瞬間、思わず画面を一時停止し、深く考え込んでしまった。
これは単なる感覚論ではない。むしろ、プロという存在が「自分の身体の変化」とどう向き合っているかを端的に示した、とても科学的な言葉だと感じた。
本コラムでは、この「週ごとにスイングを調整する」という発言を起点に、それがなぜ合理的で、トップアスリートにとって不可欠な戦略であるのかを、医科学的な視点から掘り下げていく。
■ 同じ身体は、二度とない
まず大前提として、人間の身体は、常に変化している。
-
前週の試合の疲労が残っている
-
時差や移動によって睡眠や自律神経のバランスが乱れている
-
天候や気圧の影響で関節の動きが変わっている
-
緊張や不安、期待といった感情が筋出力に影響している
これらすべてが、「いつも通りのスイング」を困難にする。それでも“同じように振らなければならない”と信じているのは、
アマチュアや未熟な指導現場にありがちな、「再現性信仰」の副産物である。
一方で、西郷プロは“日々ズレが生じ可能性”を前提にして調整する。そこに、真のプロフェッショナリズムを感じた。
■ 「調整する」という知性と神経の働き
スイングの再現性を支えているのは、「脳内の予測モデル=インターナルモデル」である。
これは、「こう振れば、こう動く」という予測を脳が無意識に構築し、そこに合わせて筋肉を動かす仕組みのこと。
しかし、体調・関節の可動域・筋の反応スピードは日々変わる。
よってプロは、毎回微細にモデルを“再学習”しながら調整している。これこそが、“プロは感覚が鋭い”という表現の正体だ。
感覚ではなく、脳と身体の適応能力が高いのである。
西郷プロが「少しづつ調整してく」と言ったのは、このインターナルモデルを更新する“セッション”に他ならない。
■ 「整える」ために変える。それがプロのスイング哲学
アマチュアが「変えてはいけない」と思っているスイングを、プロは「変えながら整える」ものとして扱っている。
-
可動域が狭ければテークバックの大きさを変える
-
下半身が不安定ならスイングテンポを落とす
-
疲労感が強ければ、クラブを軽めに持つ
その判断は、感覚と科学の間で行われる調整作業であり、決して適当なものではない。
むしろ、毎週同じように打とうとする方が、身体に無理を強いる“非科学的行動”なのだ。
■ 固定しない、自分の型をその週に合わせて作る
西郷プロのようなトップ選手が、毎週自分を更新している。これは、アマチュアが思っている以上に重要な示唆を含んでいる。
「身体は、思っているほど安定していない」
「だからこそ、整えるという行為が大切」
「整えるとは、“変えることを受け入れる”こと」
プロのスイングが美しいのは、型を守っているからではない。その週に最も適した“型”を、自分でつくっているからだ。
■ 結びに──“自分の今”を許す強さ
「今日は調子が悪いから仕方ない」と言ってしまう人は、自分の身体を“昨日までの理想”に押し込めようとしている。
でも、プロは違う。
「今日の自分はこうだから、こう動かす。」
「いつもの形にはこだわらず、今日勝つための形を組み立てる。」
それは、“自分の今”を冷静に受け入れるという、最高の柔軟性と最強の自律神経コントロールの証だ。
西郷真央プロのあの一言には、プロゴルファーの本質が凝縮されていた。
一人でも多くのゴルファーの役に立ちますように!
メジャーチャンピオン西郷真央プロ ”静かなる頂点”vol.749